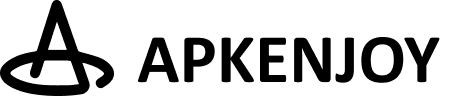日本では今なお、理系学問と女性に対するジェンダーバイアスが根強く残っています。特に「工学は男性の領域」「女性は数学や科学が苦手」といった偏見が、女性の進学やキャリア選択に影響を与えてきました。このような状況を打破し、女性の工学分野進出を促進するために、いくつかの大学が取り組みを強化しています。その一例として、奈良女子大と芝浦工業大が挙げられます。
奈良女子大の工学部設立とその影響
2022年、奈良女子大は日本初となる女子大内の工学部を設立しました。この試みには多くの懸念もありましたが、予想に反して初年度の入学試験では倍率が4倍を超え、全国から学生が集まりました。藤田盟児教授は、当初の不安が杞憂に終わったことを振り返りつつ、「女性が工学を学ぶための環境が整うことで、より多くの学生が進学を決断した」と述べています。
奈良女子大では、工学部設置にあたり、アメリカの工科大学を調査し、女性の学生比率が高い要因を分析。結果、「工学は社会貢献のためにある」という理念を掲げ、一般教養を含めた幅広いカリキュラムを採用することで、学生たちに自分の強みを見つけ、社会貢献への道を模索する機会を提供しています。
芝浦工業大の女性学生比率増加
芝浦工業大も、かつて男性が主流だった工学部の改革に取り組んでいます。約10年前から始めた改革の一環として、女性学生の割合を増やすための施策を講じてきました。特に注力したのは、私立女子高校との協定による出張授業やインターンシップの開催です。また、オープンキャンパスや女性向けのホームページを通じて、先輩学生の活躍を紹介し、女性学生が進学を決める際のロールモデルを示しています。
これらの取り組みが実を結び、2014年に13.8%だった女性比率は、2024年には21.8%にまで増加しました。さらに、女性枠の導入により、入学者数の増加が続いています。
依然として低い日本の工学部女性比率
しかし、日本全体の工学部における女性比率は依然として低く、2024年時点で四年制大学全体の女性比率が45.9%に達したのに対し、工学部はわずか16.7%にとどまっています。国際的な比較でも、日本はOECD加盟国38カ国中、工学・製造・建築分野における女性卒業生比率で最下位に位置しています。2021年のデータによると、日本は16%に過ぎず、最も高いアイスランドやポーランドは41%に達しているのに対し、加盟国の平均は28%です。
改善のために求められる社会的な取り組み
この状況を改善するためには、社会全体で性別に基づく偏見をなくし、女性が理系分野に進学しやすい環境を整えることが重要です。九州大学の河野銀子教授は、まず大人世代が自らの意識を改革し、「性別に基づく思い込みに気づき、改めることが大切だ」と強調しています。
さらに、大学や国の取り組みが求められています。特に、女性が魅力を感じる教育内容の提供や、学びやすい環境づくりが重要です。河野教授は、理系分野への進学を性別に関係なくサポートする社会が必要だと訴えています。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement