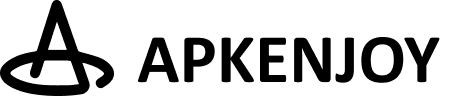早くスムーズに昇進するためには何をすればいいのか。マネックスグループ取締役でAI研究者、小説家でもある山田尚史さんは「卓越したマネージャーや責任感の強いリーダーは、社内面談で『最近困ったことはありますか』と質問したときの回答が違う」という――。
■スペシャリストとジェネラリストのどちらを目指すか
人事評価や採用面談だったり、あるいはメンターとしてキャリア相談に乗ったりするときに、特にエンジニアに関して悩みが多いのは、スペシャリストとジェネラリスト、どちらを目指すべきかということである。それは言い換えると、技術を極めて突き抜けるべきか、マネージャー職にキャリアを軌道修正すべきか、という葛藤のことが多い。
あまりエンジニアの生態に詳しくない人も多いだろうから簡単に説明すると、エンジニアの多くは自分の技術に自信を持っており、自分より技術がわからない人に自分の技術力を評価されることをひどく嫌がる。多少誇張した表現だし、例外的な人ももちろんいるのだが、この方針でいくと、人事評価の役割を持てるのは一番優秀なエンジニアだけ、ということになってしまう。
しかし一方で、ずっとエンジニアのキャリアを積み上げてきた人にとって、マネージャーになるというのは転職に近い。例えるなら、突然経理部や法務部に配置転換されるのと同じように感じるのである。また、マネジメントというのもやはり技能が必要で、向き不向きがあり、特にコミュニケーションスタイルの点で、エンジニアとして日々こなしてきた仕事と相性が悪い場合もある。
■エンジニアがスペシャリストを目指すのも茨の道
適性を見るために試しにやってみようという考え方もあるが、マネージャーになるというのは役割上出世のように見えてしまうので、やってみてダメでした、とメンバーに戻すのも収まりが悪かったりする。それに、新しい役割やそれに必要な技能を身に付けるにあたって、その人自身がそのキャリアを能動的に選択したのでなければ、多くの場合失敗につながってしまうだろう。
結果的に、エンジニアの多くは、スペシャリストを目指したい、という人が多いように見受けられる(グーグルの検索窓に「エンジニア マネージャー」と入れてみたところ、サジェストの一番上は「エンジニア マネージャー やりたくない」だった)。ただ、私の個人的意見からすると、スペシャリストを目指すのも、なかなかに茨の道である。
理由はいくつかあるが、まず、昨今の技術のライフサイクルの短さが挙げられる。今使われている技術が、5年後10年後も同じ重要さで引き続き使われている可能性はかなり低い。サーバー技術者を見てみても、15年前は自分でラックを組み立てられる人の需要はいくらでもあったが、今はクラウドが一般化していて、仮想サーバー、あるいはコンテナの設定ができる人の方が需要がある。もちろん基盤側には引き続きスペシャリストが必要であるし、培ってきた技術が無駄になるわけではないのだが、その椅子の数が大幅に減っているのは否定しようがない。
■マネージャーになる方が食いっぱぐれない
こうした変化にもついていけばいい、という考え方もあるが、もう一つの理由として、変化する技術への追従がライフスタイルの変化に伴い難しくなっていくのではないか、ということが挙げられる。これも人によるので、大まかな傾向に過ぎず、あてはまらない人もいるだろうが、例えば結婚したり、子供ができたりすると、休日の勉強時間は減っていく。エンジニアの多くは職場だけではなく、就業後や休日に技術研鑽をしている。確かに積み上げてきた知識はあろうが、自分の数倍の可処分時間を持っている人と、変化の速い業界で戦うのは不利だ。
スペシャリストにこうした事情があるのに対して、ジェネラリストはどうだろうか。正直に言って、マネージャーに移っていくキャリアの方が食いっぱぐれないように私は思う。直感的にはマネージャーが必要なのは数人に1人の割合なので、そちらの方が椅子が少ないように思うのだが、エンジニアが増える速度の方が速いので、どの会社でもいいマネージャーは人手不足である。
■いろいろな可能性を検討したほうがいい
それに、マネージャーといっても人を含めたチームをマネジメントするエンジニアリングマネージャーに限らず、プロジェクトマネージャーやプロダクトマネージャーといったキャリアもある。他にも、私のように経営者として、CTOやCEOを目指すといった道もある。加えて言えば、AIによってエンジニアの生産性が向上する世界において、重要なのは「どうやって作るか」ではなく「何を作るか」である。そして、それを決めるのはまさしくプロダクトマネージャーに他ならない。
さらに、『RANGE(レンジ) 知識の「幅」が最強の武器になる』(デイビッド・エプスタイン著/東方雅美訳/日経BP)では、ある技術に集中することで卓越するのは、チェスやゴルフなどのルールが明らかな狭い環境のみであって、ビジネスや研究などのオープンな環境では、ジェネラリストの方が大きな成果を上げる可能性があると述べられている。技術の研鑽の結果を測るにあたり、競技プログラミングに限定すると、どちらかと言うと前者の領域のように思うが、その技術を使って現実にサービスを提供したり、社会インパクトを与えたりするのは、明らかに後者の領域の問題にあたる。
そのため、やりたいことにもよるが、スペシャリストを目指す人であっても、広く能力を伸ばしていく方が、結果的に大きな成果を出せるかもしれない。東方雅美訳/日経BP)では、ある技術に集中することで卓越するのは、チェスやゴルフなどのルールが明らかな狭い環境のみであって、ビジネスや研究などのオープンな環境では、ジェネラリストの方が大きな成果を上げる可能性があると述べられている。技術の研鑽の結果を測るにあたり、競技プログラミングに限定すると、どちらかと言うと前者の領域のように思うが、その技術を使って現実にサービスを提供したり、社会インパクトを与えたりするのは、明らかに後者の領域の問題にあたる。
そのため、やりたいことにもよるが、スペシャリストを目指す人であっても、広く能力を伸ばしていく方が、結果的に大きな成果を出せるかもしれない。
■今日から使える「会社で昇進するための裏技」
こうして長々と書いてきたが、私は全員がジェネラリストを目指すべきだとは思わない。個人的には、覚悟を持ってスペシャリストを目指す人を、かっこいいと思うし尊敬する。ただ、マネージャーにはなりたくない、といった瞬間的な感情だけで大きな選択をするのは短慮に過ぎると思う。いろいろな可能性やなりたい自分を鑑みて、熟考し、決意を持って未来を選択してほしいと思うのである。
精神論が続いてしまったので、もっと速攻で効果のある、実践的な昇進のための裏技を教えよう。それは、朝仕事場に入った瞬間から退勤するまで、「徹底的に主語をWeにして考え、行動する」ということである(やっぱりこれも精神論だろうか。しかし、効果は確実にある)。
■マネージャーではないのに「主語がWeの人」のすごさ
私はよく社内面談の中で、「最近困ったことはありますか?」と質問する。ほとんどの人は、“自分が”困ったことを話す。ただ、卓越したマネージャーや、責任感の強いリーダーは、必ずと言っていいほど“チームが”困ったことを話す。とはいえ、それはある意味当たり前のことで、立場が人を作るというように、チームの成果の最大化が仕事の人たちなのだから、チームを主語として考えているのは自然なことだ。
だが時に、マネージャーではないのに、初めから主語がWeの人がいる。例えば、私たちチームはこういうことをしたくて、そのために制度上こういう無駄な作業が発生してしまうので、そこを効率化できないか考えています、といった次第である。私の経験上、こうした人はすぐにリーダーやマネージャーの候補リストに入る。反対に、なんらかの事情でマネージャーに昇格したところで、一生主語がIのままの人もいる。チームの成果ではなく、自分の給与や立場が上がらなくて困っている、といった具合である。そうした人はマネジメントに問題を抱えていることも多い。
主語がWeの人は、仕事を進めるうえで他責にならないし、自分だけでなくチームのために問題解決に取り組むので、周囲からの信頼も醸成しやすい。要は、個という局所最適に陥るのではなく、チームという全体最適で考えるような振る舞いをするのである。そして、統括するチームが部署になり、事業部になり、会社になっていくことこそが、昇進であり、より大きな仕事を任せられるということである。結果的により大きな成果を出すことができ、翻って給与に反映される。
■役割が人を作る部分もある
無論、私が見ている限りでも、人が役割をこなすというより、役割が人を作る部分もある。人事の考えでは、入学制と卒業制といったようなものがあるが(前者はポテンシャルで職位をつけ、後者は十分なスキルが身に付いたことを確認してから職位をつける)、それでも先取りで視野を広げておくことに越したことはない。あなたの上司も、安心してあなたを昇進させられるだろう。
主語をWeで考えることには、少なくとも普段の仕事でマイナスの副作用はないように思う。そして、これを1日2日で終わらせるのではなく、1週間、1カ月、半年、1年と続けていくと、初めは意識的に行っていた思考法でも、繰り返せばなじむもので、自然にものごとをWeで考えられるようになるだろう。そうなればあなたの職位は自然に上がっていく……はずだ。上司に見る目があれば、だが。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement