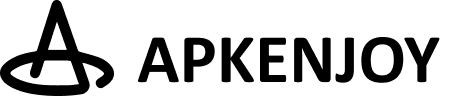2024年の出生数が72万988人と、過去最少を9年連続で更新しました。こうした中、出産費用に公的医療保険を適用する議論など、産科医療を巡って様々な動きが出てきています。全国の赤十字病院でただ一人の女性院長である東京かつしか赤十字母子医療センターの三石知左子さんに、周産期医療の現状や課題、また医療現場で働く女性たちへの思いを聞きました。俳人でもあり、ご自身の句集「小(ち)さきもの」(朔出版)から作品を織り交ぜて紹介します。
――わが国の周産期医療は世界でもトップクラスだそうですね。 手のひらにのるような500~600グラムで生まれた小さな赤ちゃんも、高度な治療で救命されるようになりました。出産年齢が高まり、NICU(新生児集中治療室)への入院が必要な新生児は増えています。それでも日本は、新生児死亡率が世界で最も低い国です。
頭から体温が奪われないよう、保育器の中でお母さんが編んだ帽子を被(かぶ)ってすやすや眠る赤ちゃんを詠みました。私は、小児科医としてNICUに配属された初日に生まれた、体重1000グラムにも満たない双子の赤ちゃんとの出会いがきっかけで周産期医療に携わることになりました。
NICUには、さまざまなリスクをもった赤ちゃんがいます。その中で、私が気になっているのが「特定妊婦」です。貧困やDV、精神疾患などの問題を抱えていて、妊娠届が提出されていなかったり、妊婦健診を受けていなかったりするケースが多いです。早産になったり、低体重で生まれたりする場合も少なくありません。児童虐待に結びつくリスクも高く、出産前はもちろん、赤ちゃんとお母さんが地域に戻った後も、医療だけでなく、保健師や児童相談所など、行政機関との情報共有や連携によるフォローが必要になります。
当院では、妊産婦コーディネーター、産科医師、産科外来助産師のほか、NICUや小児科の看護師、臨床心理士、医療ソーシャルワーカーらでチームを作り、社会的な問題を抱える特定妊婦を切れ目なく支援することに努め、地域の関係機関とも連携しています。
桜草十代の母健気なる
この句のように、若くして健気(けなげ)に産み育てるお母さんはいます。でも、10代の出産には背景に問題があるケースも少なくありません。
――今までに、どんなケースを経験されましたか。
18歳で、あと半年で卒業という時に、望まない妊娠が判明した女子高生がいました。28歳の社会人の彼とは別れた後に、産婦人科で妊娠したことと、性感染症にかかっていることが分かり、子ども家庭支援センターから当院への受診を勧められました。初診時、すでに26週相当で中絶はできず、38週目に帝王切開で出産しました。「このまま赤ちゃんと一緒にいたい。でも子育ては大変」と心を揺らしていましたが、結局、特別養子縁組の里子に出すことになりました。
また、16歳で初産、23歳で5人目の妊娠をして来院した女性は、夫は39歳で定職に就かず、生活保護を受けていました。女性の実母はアルコール依存症で、子育ての協力が得られませんでした。顔にあざがあり、シェルターへの入所を希望したこともありましたが、今も夫と子どもとの生活を続けています。地域の保健師や子ども家庭支援センターの職員に継続して見守ってもらっています。
――麻酔で出産の痛みを和らげる無痛分娩(ぶんべん)の人気が高まっています。東京都は25年10月から、無痛分娩に対する助成制度を創設します。
働く女性が増え、出産年齢が上がる中でニーズが高まっています。「痛みを我慢して、それを経験しないと立派な母親になれない」というのはただの精神論です。無痛分娩で産むとお母さんの産後の回復度合いが全然違いますし、医療技術の発達で痛みを取り除けるなら、それに越したことはありません。
ただ、麻酔科医を確保して連携し、急変時や医療事故に備えることが求められ、体制整備が急がれます。麻酔で、いきみのタイミングが分かりづらくなるために助産師のリードの仕方も変わってきますし、出産時間が長引くこともあります。
家事労働が減ったことで女性の体も変わってきたとも言われています。妊娠出産は女性の体にとって一大事。当院でも助産師に資格を取ってもらい、妊婦向けのエアロビクスやヨガの教室を開いていますが、妊娠前からの体作りも必要です。
片かげをはみだしさうな妊婦かな
道にできた小さな日陰でさえ選んで歩きたい夏に、その日陰からはみ出すくらい、おなかがせり出したお母さんです。これは夏の句ですが、どんな季節でも変化する体と付き合いながら過ごす毎日は大変です。応援する思いから生まれた句です。
――出産に公的医療保険を適用するという議論も出てきています。
現場が対応しきれるか心配です。産科は自由診療といっても、365日24時間態勢で、医師や助産師の人件費がかかります。設備投資なども考えると、診療報酬にすることで経営悪化を招きかねず、地方の小さな産院などは閉院してしまう恐れもある。産科医の減少に拍車がかかるかもしれません。大きな病院へと集約が進み、地方が切り捨てられることにつながりかねないかと懸念しています。
――全国で91ある赤十字病院でただ一人の女性院長だそうですね。
先代の院長に「見える世界が違う、一度そこに立ってみたら絶対に面白い」と言われました。確かに大変なこともありますが、やりがいも感じています。
頑なに前例踏襲梅雨寒し
「頑(かたく)なに前例踏襲」が男性特有とは限りませんが、全国の赤十字病院長会議などに行くと私だけが女性。どう扱っていいのか困るようで、誰も話しかけてこないんです。そういうときは自分から入っていく。院長というのは案外孤独ですから、近隣の院長にも声をかける。男性の方って結構、人見知りで互いに話しかけるのが苦手だったりするものですね。でも、そうやって打ち解けると愚痴を言い合ったり、良い取り組みを紹介し合ったりして仲間になる。接着剤の役割ですね。
産院は母子センターへ花は葉に
当院の前身は1953年開院の葛飾赤十字産院です。地域に密着し、地元である葛飾区民の4人に1人がここで生まれています。2021年の新築移転に伴い、病院名を改称しました。レトロな響きになじみがあったと思いますが、「産院なのにNICUがあるんですか?」と聞かれることも多くて……。産科と小児科を備え、リスクの高い妊娠であっても、産後まで母子を支援する、今の病院の機能をきちんと表したいなと思いました。24年11月には出生14万人目となる赤ちゃんが誕生しています。
風光る新病院の大玻璃戸
玻璃戸(はりど)とはガラス窓のことです。旧産院の老朽化で土地探しから始めて、5階建て全104床の新病院に生まれ変わりました。母子が気兼ねなく過ごせるよう、全室個室にこだわりました。館内は窓から日差しがふんだんに注ぎ、1階には母子が親しめる絵本をたくさん備えた図書館も併設されています。
もう一つ、過酷な仕事をしている職員たちがくつろげるような空間を作りたいと思い、見晴らしのいい4階に職員がゆったり休憩できる食堂を設けました。全国的に産婦人科医は女性の比率が高く、当院も多くの女性が医師や看護師、助産師として働いています。しかし、医療現場では今も、女性は妊娠出産や育児のために離職を余儀なくされることがあります。女性が働き続けられるような職場環境を意識していますし、保育料の補助や勤務体系の整備も求められると考えています。
三椏の花よ女よ俯くな
いつも「女性よ、俯(うつむ)くな」と思っています。折しも3月8日は、女性の地位向上を目指す国際女性デーでした。そのテーマカラーでもある黄色が美しい三椏(みつまた)も俯くように咲きます。思わず憤慨して作った句です。
赤十字では副院長や部長に女性は増えてはきたものの、私の後に女性院長が続くかどうかは分かりません。一般社会を見ても、指導的立場である役職につく女性の比率はまだまだ低い。どんな仕事でも、現場を離れず働き続けて役職を目指してほしいと思います。何人かいれば、いろんなロールモデルができるわけですし。あなただけじゃなくて、あなたの後に続く女性のためにとても必要なことだから、と言いたいですね。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement