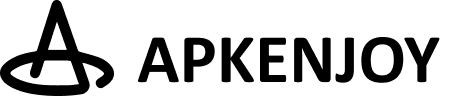2011年3月、東日本大震災で福島第一原発事故が発生した。1号機、3号機、4号機の原子炉建屋で水素爆発が起こり、大量の放射性物質が大気中に放出された。未曽有の事態に被災地のみならず、日本中が大きな不安に陥り、首都圏でも放射性物質の影響を恐れた人が少なくなかった。だが、あれから14年、放射線を原因とする死者はゼロだという。あの事故での放射線による健康への影響はどれほどだったのか。福島での県民健康調査を担当するトップのほか、関係各所を取材した。
「放射線の線量は気にしていません」
2011年3月12日、福島第一原子力発電所の1号機の原子炉建屋で水素爆発が起きた。14日には3号機、15日には4号機でも同様に水素爆発が発生。大気中にはセシウムなど大量の放射性物質が放出された。
当時、飯舘村の役場職員をしていたAさんは、こう振り返る。
「(原発から北西の位置にある)飯舘村はほとんどが30キロ圏外です。事故発生当初は、(原発が立地する)浜通りの住民の避難先として受け入れる体制をつくっていました。それが3月21日になって、水道水を飲まないよう、呼びかけがありました。基準を超える放射性ヨウ素が検出されたというのです。そのときから『ここにも危険が及んでいるのか』と不安を感じるようになりました」
4月22日に村全域が計画的避難区域となり、村民の9割以上が福島市を中心に村外へと避難した。Aさんも福島市へと移って、生活することになった。
飯舘村の避難指示が帰還困難区域を除き解除されたのは2017年3月。震災前の人口は約6500人。現在、住民基本台帳上は約4500人の住民がいるが、実際に帰還した人は1200人弱にすぎないという。Aさんは現在も避難先の福島市に居住し続けており、飯舘村にある自宅には定期的に訪れる程度だという。
Aさんが帰還していないのは子どもの学校の関係であって、放射線の問題ではないと語る。
「生活圏はしっかりと除染されているからです。飯舘の人と話をしても、放射線の話題が出るのは『山奥で取れるキノコは線量が高いから食べられない』という程度。他の村民の方でも放射線の線量が気になって戻らないという人はごくわずかでしょう。大半が生活の利便性による理由だと思います。放射線の線量は気にしていません」
原発事故から14年。被災地でも放射線に対する不安は薄れている。それは、原発事故による放射線の影響が出ていないことが明らかになってきたことも理由の一つであろう。
重要なことは、放射線の被ばくによる死者は一人も出ていないということだ。
「放射線での死者はゼロ」
「単刀直入に申し上げて、(原発事故で放出された)放射性物質からの放射線による直接的な死亡が発生していないのは間違いありません」
福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センターの安村誠司センター長はこう語る。
「原発事故直後だけでなく、その後の十数年間を考えても、放射線が原因で亡くなった方は、私の知る限り、ゼロです。このことはしっかりお伝えしたいと思います」
安村氏も事故発生当初は放射線に対して恐怖を感じていたという。
「放射線は目に見えないため、精神的な不安を引き起こしやすい。私自身(居住する)福島市内で線量が高くなっていると知ったとき、恐怖を感じました。『ここにいて本当に大丈夫なのか』と悩んだこともあります。その恐怖は、見えず、においもしない放射線の特性によるものです」
放射線量を広域でモニタリングすると、単純な同心円状ではなく、飯舘村などの北西部で比較的高い線量が検出された。事故当時、事故現場では東南東の風が吹いていたためだ。当時の報道記事では、福島市役所前で3マイクロシーベルト(毎時)、飯舘村役場前では8マイクロシーベルトを超えており、森の中の山道では100マイクロシーベルトを超える場所も見られたという。
「放射能汚染」報道は過熱し、その不安は首都圏に住む人々にまで及んだ。雨や風で放射性物質がたまり、高い線量を発する場所「ホットスポット」が、首都圏にあることも報じられると、さらに不安が増強された。当時、首都圏を離れ、西日本や海外に移住した人も珍しくなかった。
放射能に汚染された食品や飲料を摂取することでの内部被ばくの危険性も盛んに報じられた。原子力発電所の事故の指標「INES(国際原子力事象評価尺度)」で、福島第一原発事故はレベル7とされたことも不安を高めた要因だった。レベル7は1986年旧ソ連のチェルノブイリ原発事故と同じ水準だった。
政府の対応もさらに不安を招いた。当時の枝野幸男官房長官は連日の会見で、放射能の影響について「直ちに人体(健康)に影響はない」と繰り返した。文部科学省が20〜30キロ圏のモニタリング調査の結果を発表した3月16日の記者会見でも枝野氏は、「365日、24時間屋外でこの数値の場所にいた場合に、問題が出るかもしれないといったレベルで、こうした地域に数日いて人体に影響を及ぼすといった数字ではない」と語っている。だが、こうした発言を素直に信じる人は多くなかった。
あれから14年、放射線による影響はどう評価されてきたのか。
「県民健康調査」で見る健康への影響
福島県では2011年から「県民健康調査」を実施してきた。同年3月11日から同7月11日まで「いつ」「どこに」「どのくらいいたか」という問診票によって外部被ばく線量を推計する「基本調査」をするとともに、必要に応じて一般健診の「健康診査」、18歳以下の「甲状腺検査」、「こころの健康度・生活習慣に関する調査」、「妊産婦に関する調査」(2020年度まで)という詳細な4調査を行うというものだ。
2024年度版の同「報告」で、回答率は27.7%。放射線業務従事経験者を除いた約46万7千人の外部被ばく線量の推計で99.8%の人が5ミリシーベルト未満、最高値は25ミリシーベルトだったと公表。次のように評価している。
<この結果については、これまでの疫学調査により、100ミリシーベルト以下での明らかな健康影響が確認されていないことから、4か月間の外部被ばく線量推計値ではありますが、放射線による健康影響があるとは考えにくいと評価されています>
この県民健康調査を疫学的な観点で担当してきたのが、前出の安村氏だ。安村氏も放射線による直接的な健康被害はないとしつつ、次のように語る。
「放射線による直接的な影響で重大な事例はありませんが、事故による間接的な影響はあります。原発事故の影響で、福島県では二十数万人が避難しなければならなくなりました。この避難の過程で、もともと病気を抱える方や高齢者など県民の方々には多大な影響がありました。放射線による健康影響はありませんが、原発事故による影響はそれなりにあったということです」
県民健康調査で2ミリシーベルト未満が93.8%
そもそも、原発事故で大気中に放出された放射性物質は人体にどのような影響を与えるのか。環境省や各種医学的知見によると、こういう仕組みだ。
セシウムやヨウ素といった物質は放射線(ベータ線、ガンマ線など)を出す。その放射線が一定の線量で生体を通過すると、細胞内のDNAに影響を及ぼす。DNAが放射線の電離作用で直接的に広範囲に切断されたり、放射線のせいで発生した活性酸素によって間接的に損傷されたりするのだ。DNAは自然に修復されるものもあり、自然現象としての細胞死で健康に影響を与えない場合もあるが、不完全な修復のまま異常な細胞がつくられると、がんなどの原因となることがある。
では、具体的にどのくらいの放射線を浴びたら危険とされるのか。国際放射線防護委員会(ICRP)の2007年勧告によると、累積の被ばく線量が100ミリシーベルトを超えると、がんの発症率が増加することが確認されている。長年の調査研究から世界的に信頼されている基準だが、もとはといえば、広島と長崎の原爆による被ばくの研究が土台だと安村氏は言う。
「広島・長崎の原爆データから推計された線量効果関係は、線量が増えると健康影響の確率が上がるということでした。もちろん、100ミリシーベルト以下なら確実に安全と言い切るつもりはありません。それでも、100ミリシーベルトを超えると集団の中で影響が検出されるレベル、という理解でいいと思います」
前述の県民健康調査では約210万人いた県民全員を対象にしたが、調査に回答したのは約47万人。2ミリシーベルト未満が93.8%で、5ミリシーベルト未満では99.8%、15ミリシーベルトを超えた人は323人だった。
「私たちが調査した範囲では最大でも25ミリシーベルトで、100ミリシーベルトを超えて浴びた人が一般県民の中にいたという報告はありません。国際機関もその点を認めています。外部被ばくについては直接的な健康影響は考えにくい状況です。内部被ばくについても、いろいろな推計を行っていますが、100ミリシーベルトを超える線量の被ばくがあったという報告はないと理解しています」(安村氏)
国のほうも調査や評価を進めてきた。国は福島第一原発事故後の健康管理について、医学的な見地から検討が必要として、2012年に調査をするよう法的に整備した。2013年、環境省に「東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う住民の健康管理のあり方に関する専門家会議」を設置し、医師や放射線など17人の専門家により、14回にわたって会議を開催した。
この会議では、2014年12月に「中間取りまとめ」が発表されたが、そこではこう報告されている。
<今回の事故による放射線被ばくによる生物学的影響は現在のところ認められておらず、今後も放射線被ばくによって何らかの疾病のリスクが高まることも可能性としては小さいと考えられる>
国連科学委員会の報告書
一方、こうした報告に違和感を抱いている人もいる。2011〜2019年度に行われた県民健康調査で、事故当時18歳以下だった人を対象に甲状腺検査をしたところ251人(うち7人は25歳)が甲状腺がんかその疑いがあると診断された。専門家でつくる評価部会は過剰診断であって、被ばくとの因果関係は認められないとしたが、納得がいかない人たちはいた。
2022年1月、事故発生当時、福島県内に居住していた17〜27歳(当時6〜16歳)の6人が、小児甲状腺がんを発症したのは福島第一原発事故が原因として東京電力を相手に、総額6億1600万円の損害賠償を求めて提訴した。2人は甲状腺の片側を、4人が再発で全摘したとしている。
ただ、欧米などの科学者で構成される団体は、こうした因果関係を否定している。
国連の「原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)」は2021年に報告書を公開、この中で福島第一原発事故と放射線の被ばくの影響について詳細に科学的な知見で調査、甲状腺がんとの因果関係についても「放射線被ばくに帰因する甲状腺がんの過剰リスクは、どの年齢層においても識別できる可能性はほとんどないことが示唆されている」(同報告書83ページ)と述べている。
環境省や復興庁もこうしたUNSCEARの報告書をもとに「現時点では、放射線の被ばくによる健康被害は認められていません。事故後の被ばく線量を鑑みても、今後の健康影響は考えにくいと評価されています」という立場をとっている。
県民健康調査は現在でも続けられているが、安村氏は続けることのデメリットも懸念している。
「たとえば、事故後『福島で赤ちゃんを産むのは危険だ』という風評がありました。ですが、10年に及ぶ調査結果では、先天奇形率や早産率は全国平均よりも低いくらいでした。この結果をもとに妊産婦調査は終了しました。調査を続けることで『何か問題があるから続けているのでは?』という誤解が生じることを防ぐためです」
原発作業員は大丈夫だったのか
一方、原発事故の作業にあたった人たちに健康被害はなかったのだろうか。安村氏は言う。
「所管が違うためすべてを把握しているわけではありませんが、作業員が重大な健康被害を受けたという情報は特に入っていません」
福島第一原発事故後の作業に従事した人のうち、被ばくとの因果関係を認めた労災認定が出た疾患は、これまでに白血病5件、真性赤血球増加症1件、咽頭がん2件、甲状腺がん2件、肺がん1件がある。そこで東京電力に取材したところ、次のような回答を得た。
「当社は、法令を順守し、線量限度はもとよりALARA(注:as low as reasonably achievable。合理的に達成可能な限り低く抑えるべきである)の考えに基づき、線量低減に努めているところであり、UNSCEAR報告書にあるように『被ばくによるがんの発生率の上昇が識別可能となるであろう可能性は低い』と認識しています。一方で、被ばくとがん症例との因果関係が科学的に証明されたことを意味するものではありませんが、事故後の作業従事者のがん症例が10件以上労災認定されていることも事実です」
東京電力が公表する資料によると、事故のあった2011年3月には108人が月間100ミリシーベルトを超える被ばく、このうち6人は月間250ミリシーベルトを超えていたという。しかし、翌月以降は100ミリシーベルトを超えた従業員はおらず、50ミリシーベルトを超えた従業員も累計で8人しかいないという。
こうした被ばく線量の把握も踏まえ、東京電力は原発作業員への健康管理について次のような見解を示した。
「IAEA(国際原子力機関)及び各国の専門家からなる調査団のレビュー(放射線防護の観点も含む)を継続的に受けており、当社の取り組みが基本的に妥当と評価いただけたものと認識しています」
死者はゼロでも、風評被害との闘いは続く
現状から見て、放射線による健康被害がゼロだったと断ずることはできない。それでも医学的および科学的な知見から見て、放射線被ばくによる死者はゼロではあり、当初懸念されていた健康被害が大きく抑えられたのは確かだろう。
安村氏はその原因をこう語る。
「レベル7という最悪の『深刻な事故』という評価を受けたため、福島第一原発事故はチョルノービリ(チェルノブイリ)と同じような事故と誤解されがちです。しかし、実際の放射性物質の放出量はチョルノービリの5分の1程度であり、避難も早期に行われました。また、チョルノービリでは放射性物質を含む食物を摂取したことが甲状腺がんの原因でしたが、福島では当初から飲食制限が行われ、被ばくの経路は限られていました。そのため、福島で同様の健康影響が出る可能性は非常に低いと考えられます」
また、住宅や道路、農地などの除染も徹底して行い、除染事業が完了した地域から帰還が始まった。それでも、福島に依然「汚染されている」といった印象を持つ人もいる。
安村氏は今後そうした風評被害をなくしていくのが重要だと言う。
「作物や海産物で安全なレベルであるにもかかわらず、根強い誤解が残っています。そうした風評被害を減らすためにも、私たちは引き続き正確な情報を発信していく必要があります。県民の健康を守るために行ってきた調査や検査の結果をもとに、福島の現状を正しく伝えていくことが大切だと考えています」
原発事故から14年、福島は復興に向けてまだ道半ばである。その復興を後押しするには、多くの人が「福島の現状」を理解していくことが重要だ。
小川匡則(おがわ・まさのり)
ジャーナリスト。1984年、東京都生まれ。講談社「週刊現代」記者。北海道大学農学部卒、同大学院農学院修了。政治、経済、社会問題などを中心に取材している。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement